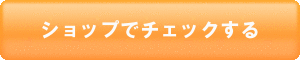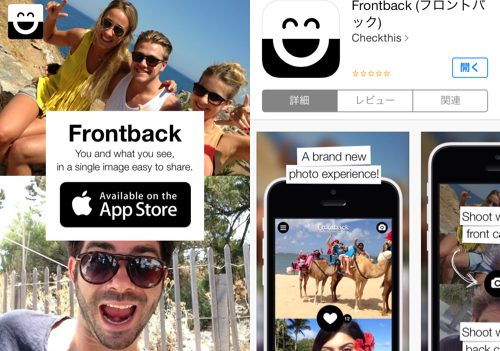山崎亮さんによるコミュニティデザインについての『夕学五十講』講演を聴き、気づいた学びのポイントをまとめます。
■山崎亮さんによる「夕学五十講」の講演
先日、「夕学五十講」という講演セミナーに参加して来ました。講師は山崎亮さん、テーマは『問題解決メソッドとしてのコミュニティデザイン』でした。
昨年11月から武蔵小杉で朝活イベントを主催したり、地域の色々な活動に参加したり、活動を運営する方とお話しする機会が多くあったりと、
地域コミュニティに関する今回のテーマは、意図せずタイミングの良い受講となり、今後の活動の役に立つことはないか?という観点で参加して来ました。
第23回 1/21(火) 山崎亮さん | 慶應MCC「夕学五十講」楽屋blog
『コミュニティデザイン』とは、
地域や公共の問題や課題を、それらに関わる人との対話を通じて解決への糸口を探し、デサインの力によるアプローチで問題解決をする手法だそうです。
講演は、山崎さんがこれまで対応されてきた『コミュニティデザイン』についての事例紹介を中心に進行していきました。
例えば、印象に残った事例は、
- 公園内に市民活動場所を取り入れた兵庫の有馬富士公園
- 地方百貨店内フロアに市民活動場所を取り入れた鹿児島マルヤガーデンズ
- マンガと市民活動をコラボした立川市子ども未来センター
- facebookページ「今宵もはじまりました」が予想外のムーブメントを巻き起こした香川観音寺商店街
などなど、どれも興味深くて面白い事例紹介ばかりでした。
その中で個人的に、どの事例にも共通する問題解決メソッドではないか?と感じたのは、以下の3つでした。
- 【1】まず聞くことが大事
- 【2】膨大なケーススタディインプット
- 【3】解決への要素を組合せる
順にその内容をまとめると、、
【1】まず聞くことが大事

対話を通じ、浮き彫りになる問題や課題に住民自らが気づいたり、当事者意識を持ってもらったり、人と人としてのつながりで信頼感を深めていくことで、
自然と解決に必要な情報が集まるようになり、解決への実行力が高まっていく事が多いそうです。
とにかく、うなづきながら、話をじっくり聞くことがポイントだそう。言わゆる「傾聴」ですね。
【2】膨大なケーススタディインプット
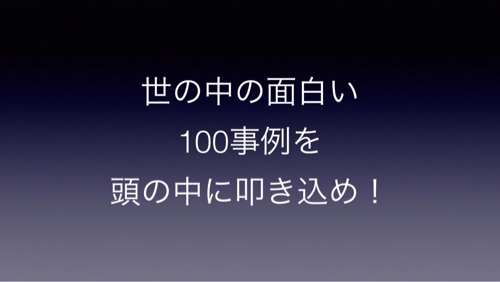
とにかく、片っ端から「事例情報」を頭に叩き込むそうです。これにより状況判断が出来るようになるとのこと。
具体的には、
ネット等で100事例を1事例1枚ずつにまとめたら、その中で面白い10事例について、さらに別メディアからの情報で枚数を増やし、さらに抜群に面白い3事例については、実際にコンタクトを取り、現地に赴いて話を聞きに行くそう。
そういった膨大な量のケーススタディの蓄積により、仕組みや要素の組み合わせで、「リデザイン」出来るようになるとのこと。
建築家やデザイナー事務所の本棚に、膨大な量の作品集などを見かけますが、デザインの現場では、当たり前のように行われるメソッドのようです。
これは、日常生活でも、何かやりたい!こうなりたい!と思った時に役立つメソッドだと思いました。
【3】成功プロジェクトの共通点
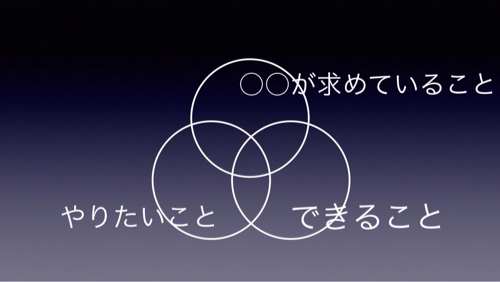
インプットした情報を整理し、「やりたいこと」「できること」「○○○が求めていること」の組み合わさるところに問題解決策を見出すことが多いそう。
○○○の部分に、色々な関係者を当てはめていき、組み合わせをひねり出していくそうです。
確かに、紹介された事例のどれもが、この組み合わせの解決策になっているように思いました。
◼︎求められてもいない事をやる価値
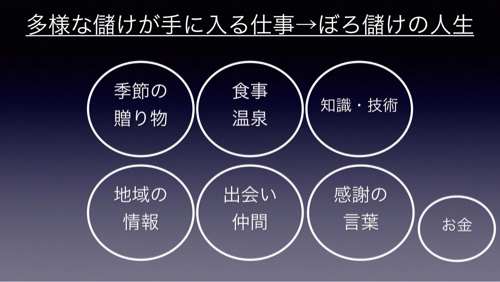
講演の最後のほうに「儲け」という印象深いキーワードの話がありました。
コミュニティデザインは、誤解を恐れずに言うと、言わば「はじめは頼まれてもいないシゴト」であり、
それをやる価値は、お金ではなく、それ以上に恩恵のある様々な価値に魅力があるとのこと。
もちろん、その価値が最初からの主目的という訳では無く、結果的に価値になっているように感じるという話です。
これは、コミュニティ活動をはじめ、色々と当てはまる事が多いなと感じました。私が、このブログをやっているのも、朝活イベントを主催し始めたも、同じような価値に魅力を見出しているからのように思いました。
以上、大変勉強になって、楽しかった講演のまとめでした〜(^^)
▼情熱大陸の出演回
▼その他の事例がたくさん
▼気になる東北でのコミュニティデザイン学科設立。別学科に小山薫堂さんも。
g*g Vol.25 SUMMER 2013:芸工大*芸術市民 | g*g
▼関連書籍
 この記事は、『するぷろ for iOS(ブログエディタ)』で書いてます。
この記事は、『するぷろ for iOS(ブログエディタ)』で書いてます。