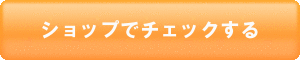「slack」という次世代メッセージングツールが、オンラインでのコミュニティ活性化に役立っています。その活用方法をまとめます。
オンラインコミュニティを盛り上げたい!
2〜3カ月前くらいから、色々と共通点が多い数人のブログ好きなメンバーと仲良くさせてもらっていて、ビデオチャット等を楽しんでいるのですが、せっかくの縁なので、仲間内だけの情報交換がもっと気軽にできる「オンラインコミュニティ」を作りたいと思っていたのです。
これまでTwitterで各々オープンに繋がっていて、Messengerのグループチャットでクローズドな仲間内やりとりをしていました。
ただ、Messengerは連絡くらいが限界と感じていて、仲間内だけの情報交換には、facebook非公開グループを使ってみようかと思っていた矢先に、「slack」の魅力を知りました。
slackとは何か?
slack.com

slackとは、開発系エンジニアが主によく使っていると言われる「北米発の次世代グループメッセージングツール」になります。このツールの登場で、もはや「メールの時代は終わった」との声もあるとか無いとか。
グループメッセージングツールで代表的なMessengerやLINEは、複数人が1つの場所に書き込む形式となりますが、このslackは、書き込む場所(=channelと呼ぶ)を任意に複数作成できるのが1つの特徴となります。
また、PCからでもスマートフォンからでも使えて、洗練された使い勝手の良さが評判のツールでもあります。ちなみに、絵文字でイイね的な事も出来ます。channel毎など細かい通知設定も出来ます。
実は、最大の特徴が他にあるのですが、置いておいて、加えて、以下の記事を見つけて、slackが「仲間内Twitter」として使える!と考えるようになったのです。
Slackで簡単に「日報」ならぬ「分報」をチームで実現する3ステップ 〜 Problemが10分で解決するチャットを作ろう

『仲間内Twitter』としての使い方
通常、書き込む場所となるchannelには「話題テーマ」の名前を付けたりして使うようなのですが、仲間内Twitterとしての使い方では、メンバーの名前をつけ「個人の部屋」の位置付けにします。
例えば、次のようなchannelを作ります。
- room-junichi
- room-taro
- room-hanako
その部屋の中で、名前の人が言わば”主人”となり、Twitterのように自由につぶやきを書き込みます。
「個人の部屋」の位置付けですが、内容はメンバー間でオープンです。他メンバーが全ての部屋の内容も読めますし、書き込むことも自由にできます。
こうすることで、Twitterのように気兼ねなく自由に何でも発言できるし、気になったつぶやきだけに反応すれば良いしと、ほんとゆるーく気楽に情報交換を楽しめるのです。
まさにクローズドなメンバー間だけの居心地の良い「仲間内Twitter」が作れた訳です。
これまで、私もいくつか主催したり参加してきたfacebook非公開グループやグループチャットでのやりとりにありがちなことが、「仲間内Twitter」では、ある意味解消されているようにも思っています。
【グループチャットにありがちな嫌なこと】
- メンバーの顔が見えずらく、発言しにくい
- 誰かが発言すると、反応しなきゃ的な雰囲気を感じる
- 主催者が、質問やトピック立てをしないと盛り上がらない
- 一部の人だけが盛り上がって、置き去り感がある
- 複数の話題を同時進行しづらく、そして把握しずらい
- 自分に関係無い話題の通知が煩わしい
- 既読プレッシャーがある
もちろん、メンバー規模や親密度、貢献度合にも依るとは思うのですが、時が経つにつれて徐々に居心地が悪くなって、読むだけメンバーになって、盛り下がって見える事が多い気がするのです。
slack導入へのハードルは何か?
実はまだslackの使用を開始して数日しか経過していないのですが、メンバーの皆さんには好評を頂いていて、やりとりを楽しんでいます。
中でも、ちょっとしたブログ運営トラブルで困っている事を何気なくつぶやいたメンバーが、偶然同じような経験があった他メンバーからのアドバイスで即解決し、それがそのまま1つのブログ記事のネタになったといったことが発生しました。
私も驚きでしたが、導入わずか数日でこんなミラクルが起きるなんて思いませんでした。
メンバーの皆さんも導入当初は、恐らくは正直なところ、半信半疑だったと思うのです。
でも、メンバーの皆さんは、新しいツールを使うことに対して、「別に合わなかったら止めれば良いだけの事。新しいもの好きだし、使ってみたい!」と、前向きに受け入れてくれたのが、オススメした者としては、とても救いでした。
実はこのslackは、表記が「英語」です。
使い勝手が非常に良く、結果的には慣れの問題とはなるのですが、英語以上にハードルになるのは、自分だけでなく、複数人で活用してこそ真価が問われるツールなだけに、「新しいツールを、受け入れられるかどうか?の抵抗感」が大きなハードルになるように感じます。
外部連携機能の面白い活用を考えるのが楽しみ
実は、まだ使い始めて数日ということもあり、現時点でslack最大の特徴である『外部サービス連携機能』が、十分に活用出来ていません。
この外部サービス連携機能とは、自分達が自ら書き込まなくても、設定や条件に応じて連携した外部サービスからの情報が自動的に書き込まれる機能になります。
開発系エンジニアにslackが人気なのは、この機能によるアイデア次第な自由度の高さにあるように思います。
ただ、私たちは現状、この機能を十分に使わなくても楽しめているので問題無いのですが、何か面白い使い方が確立できたら、別の機会に紹介出来たらと考えています。それも楽しみです。
以上、オンラインコミュニティ活性化のヒントに是非(^^)!slackオススメです。
@jun1log いや、クローズドとオープンの間にある何かが面白いのかも知れない。そして同じく、ソーシャルとリアルの間も。
— じゅんろぐ (@jun1log) February 11, 2016
▼関連するslack記事はコチラ
「おみくじ」から始める標準slackbot活用アイディア3例
▼ヒントがありそうなslackのkindle本
 Slack for Start-Ups : 70 techniques to boost your team (English Edition)
Slack for Start-Ups : 70 techniques to boost your team (English Edition)Maxime Pierrot
Blue Mountains Press
価格:599円(記事公開時)


 この記事は、『SLPRO X for iPhone(ハイブリッド・ビジュアルブログエディタ)』で書いてます。
この記事は、『SLPRO X for iPhone(ハイブリッド・ビジュアルブログエディタ)』で書いてます。